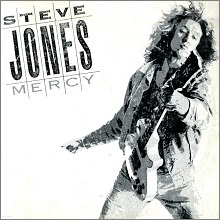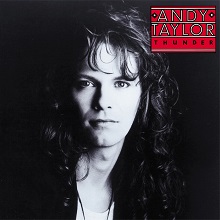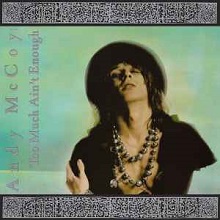AC/DC
origin: Sydney, Australia
High Voltage

1st studio album
released: 1975
- Side one
- Baby, Please Don't Go
- She's Got Balls
- Little Lover
- Stick Around
- Side two
- Soul Stripper
- You Ain't Got a Hold on Me
- Love Song (Oh Jene)
- Show Business
[comment]
母国オーストラリアでのデビュー・アルバム。
豪州盤なので、正直なところ、殆どの日本のロック・リスナーにとって、馴染みの薄いアルバムだ。
"She's Got Balls"、"Little Lover" の2曲が、後の世界デビュー盤の High Voltage に収録されている。
T.N.T.

2nd studio album
released: 1975
- Side one
- It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)
- Rock 'n' Roll Singer
- The Jack
- Live Wire
- Side two
- T.N.T.
- Rocker
- Can I Sit Next to You, Girl
- High Voltage
- School Days
[comment]
母国オーストラリアでの2ndアルバム。
これも豪州盤なので、殆どの日本のロック・リスナーにとって、馴染みの薄いアルバムだ。
"It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)"、"Rock 'n' Roll Singer"、"The Jack"、"Live Wire"、"T.N.T."、"Can I Sit Next to You Girl"、"High Voltage" の7曲が、後の世界デビュー盤の High Voltage に収録されている。
High Voltage [ハイ・ヴォルテージ]

1st internationally released album
released: 1976
- Side one
- It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)
- Rock 'n' Roll Singer
- The Jack
- Live Wire
- Side two
- T.N.T.
- Can I Sit Next to You Girl
- Little Lover
- She's Got Balls
- High Voltage
[comment]
既にリリース済みの 2枚の豪州盤、High Voltage と T.N.T. からセレクトした世界デビュー盤。
表題曲の "High Voltage" は、High Voltage ではなく、T.N.T. の収録曲だというややこしさ。
殆どの日本のロック・リスナーにとって、AC/DC のデビュー・アルバムといえば、これだろう。
今の AC/DC にも脈々と受け継がれるブルーズ・ベースのロックン・ロールであり、AC/DC というバンドは、ここから殆ど変っていない。
強いて言うなら、70年代的なハード・ロックよりは、60年代的なブルーズ・ロックに近い。
Dirty Deeds Done Dirt Cheap [悪事と地獄]

3rd studio album
released: 1976/09/20
- Side one
- Dirty Deeds Done Dirt Cheap
- Love at First Feel
- Big Balls
- Rocker
- Problem Child
- Side two
- There's Gonna Be Some Rockin'
- Ain't No Fun (Waiting 'Round to Be a Millionaire)
- Ride On
- Squealer
[comment]
AC/DC のアルバム解説は難しい。
何しろ、アルバムのリリースを重ねても、音楽性は殆ど変わらず、ブルーズ・ベースのロックン・ロールなのだから。
前作との違いを無理やり見つけるなら、ローカルっぽさが薄れて、メインストリーム型のハード・ロックに近づいたということくらいだろうか?
ちなみに、この時期のシンガー、ボン・スコット の歌唱にはメタリックな要素が無く、徹頭徹尾ロックン・ロール・シンガーなので、ヘヴィ・メタルを期待して聴くと、ちょっと肩透かしを食らうかもしれない。
Let There Be Rock [ロック魂]

4th studio album
released: 1977
- Side one
- Go Down
- Dog Eat Dog
- Let There Be Rock
- Bad Boy Boogie
- Side two
- Problem Child
- Overdose
- Hell Ain't a Bad Place to Be
- Whole Lotta Rosie
[comment]
ロック史上、トップクラスに入るカッコいいアルバム・カヴァー。
全てのアルバムが名盤の AC/DC だが、70年代(=ボン・スコット時代)のスタジオ・アルバムから、名盤を1枚選べと強制されるなら、これを選ぶ。
理由は、多くの人の予想通り、"Whole Lotta Rosie" が収録されているからだ。
この曲を聴いてクレイジーになれない人はロックン・ロールを語るな!...と言うのは傲慢だが、筆者にとって、この曲でクレイジーになれない人とはロックン・ロールに求めるものが違うと判断できる物差しのような曲なのである。
Powerage [パワーエイジ]

5th studio album
released: 1978
- Side one
- Rock 'n' Roll Damnation
- Down Payment Blues
- Gimme a Bullet
- Riff Raff
- Side two
- Sin City
- What's Next to the Moon
- Gone Shootin
- Up to My Neck in You
- Kicked in the Teeth
[comment]
このアルバムの収録曲はライヴで演奏されることが少なくなったため、アルバム自体の印象が地味に捉えられがちだが、実際には名曲ぞろいの名盤である。
そもそも AC/DC のアルバムは全て名盤であり、このアルバムは AC/DC のディスコグラフィの中でも脳を揺さぶる名リフの宝庫だ。
そして、AC/DC 好きの Aerosmith のギタリスト、ジョー・ペリーがフェイバリットに挙げるアルバムでもある。
前作、Let There Be Rock もロック史上屈指の素晴らしいアルバム・カヴァーだったが、このアルバムのアートワークは前作とは全く異質ではあるが、袖からコードを垂らすアンガス・ヤングが素敵すぎて、前作に匹敵するアルバム・カヴァーだと思う。
If You Want Blood You've Got It [ギター殺人事件]

1st live album
released: 1978
- Side one
- Riff Raff (from Powerage)
- Hell Ain't a Bad Place to Be (from Let There Be Rock)
- Bad Boy Boogie (from Let There Be Rock)
- The Jack (from T.N.T.)
- Problem Child (from Dirty Deeds Done Dirt Cheap)
- Side two
- Whole Lotta Rosie(from Let There Be Rock)
- Rock 'n' Roll Damnation (from Powerage)
- High Voltage (from T.N.T.)
- Let There Be Rock (from Let There Be Rock)
- Rocker (from T.N.T.)
[comment]
スタジオ盤よりもライヴ盤の方が、そのバンドの本質を表し、名演を記録している場合は意外と多く、最初に聴く1枚として適していることがある。
例えば、The Yardbirds の Five Live Yardbirds、Deep Purple の Made in Japan、Rory Gallagher の Live in Europe、UFO の Strangers in the Night 等。
70年代(=ボン・スコット時代)の AC/DC も、このライヴ・アルバムが彼らの魅力を最も分かりやすく伝えてくれるのではないだろうか?
演奏はタイトで、選曲も良く、ライヴでの AC/DC はブギーっぽさやブルーズっぽさがスタジオ盤よりも一層際立って聴こえる。
Highway to Hell [地獄のハイウェイ]

6th studio album
released: 1979
- Side one
- Highway to Hell
- Girls Got Rhythm
- Walk All Over You
- Touch Too Much
- Beating Around the Bush
- Side two
- Shot Down in Flames
- Get It Hot
- If You Want Blood (You've Got It)
- Love Hungry Man
- Night Prowler
[comment]
ボン・スコットの遺作となったアルバムであり、以外にも、これが米国でリリースされた AC/DC の最初のアルバムである。
相変わらずのブルーズ・ロック、そしてロックン・ロールなのだが、バンドの演奏力が更に上がり録音状態も良いため、各楽器の音の分離が良いので聴きやすくなっている。
簡単に言えば、「もの凄く売れそうな音になった」ということであり、世界規模での成功が約束されたような音なのである。
これの次が、ブライアン・ジョンソンが加入して驚異的なヒットを記録した Back in Black なのだが、シンガーがボン・スコットのまま次のアルバムを制作していたら、どのような音になっていたのだろう?
~ 総括 ~
筆者は1969年生まれなので、70年代のロックは全て後追いである。
つまり、AC/DC はシンガーがブライアン・ジョンソンに変ってから聴いており、最初に聴いたのは10thアルバムの Fly on the Wall であり、実はこれは AC/DC の低迷期とされる時期のアルバムだ。
しかし、筆者にとっては名盤であり、その後、Back in Black と For Those About to Rock We Salute You を聴いて、完全に AC/DC に嵌った。
当時の筆者にとって、AC/DC のシンガーとはブライアン・ジョンソンだったので、70年代(=ボン・スコット時代)の AC/DC は避けていたのだが、その壁を打ち破る切っ掛けとなったのが Guns N' Roses だった。
Guns N' Roses の日本限定の編集盤 Live from the Jungle に収録されていた AC/DC のカヴァー "Whole Lotta Rosie" を聴いて、そのあまりのカッコ良さにブッ飛ばされたのである。
これはオリジナルを聴かなければと思い購入したのが、ボン・スコット時代のライヴ盤 If You Want Blood You've Got It だ。
驚いたのは、ハイトーンでメタリックなブライアン・ジョンソンと、セクシーでワイルドなボン・スコットでは、シンガーとしてのタイプが全く異なるにも関わらず、何の違和感なく聴けたことだった。
その後はボン・スコット時代のアルバムも次々に聴いていったのだが、とにかくロックン・ロールの名盤揃いであり、ボン・スコットが亡くなりブライアン・ジョンソンにシンガーを変えてからも、音楽性を殆ど変えずに一貫してロックン・ロールを演奏し続け、これほどファンから愛され続けているバンドは稀有なのではないだろうか?
AC/DC の凄さとは、長期に渡りロックン・ロールをやり続け、常にタイトで高水準なライヴをファンに提供しているところだ。
例えば、New York Dolls や The Stooges 等も優れたロックン・ロール・バンドであり、筆者にとっても重要なバンドなのだが、彼らは自堕落でドラッグに惑溺したためバンド活動が短命に終わっており、そのあたりが甚だ残念なところだ。
それと比べると、AC/DC の場合、ドラッグの問題を抱えたドラマーのフィル・ラッドを解雇する潔さがあり、バンドを運営する能力が高い。
一面的に見ると冷たい印象を与えるかもしれないが、バンド運営に関わっているクルーの生活や、レコード会社やマネジメントのスタッフの生活があるのだから、一人のメンバーの不祥事で多くの関係者を路頭に迷わすわけにはいかないので、これは極めて真っ当な判断なのである。
長きに渡り活動を続けてきた AC/DC だが、リズム・ギタリストのマルコム・ヤングは認知症でバンドを離れ、2017年に死去した。
シンガーのブライアン・ジョンソンは聴力障害で一時期バンドを離れている時期があった(代役は Guns N' Roses のアクセル・ローズ)。
バンドの顔であるリード・ギタリストのアンガス・ヤングは、2024年3月31日で69歳になった。
ベーシストのクリフ・ウィリアムズは70歳を超えており、ドラマーのフィル・ラッドも間もなく70歳になる(フィル・ラッドはドラッグ問題でバンドへの出戻りを2回繰り返しているので危うい)。
何となくバンド活動が終焉に来ているような気がする。
いつまでバンドが続くか分からないのだが、彼らがバンドを続けてくれる限り、筆者は追いかけようと思っている。