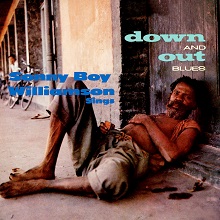富と名声を求めてロック・ミュージシャンを志すというのは、よくある話だ。
それが悪いことだとは全く思わない。
「Sex, Drugs & Rock 'n' Roll」という言葉があるように、そもそもロックとは享楽的なものであり、普通ではない「狂気」が横行する世界なのだろう。
今回取り上げた作品は、そんな狂気の世界の住人となってはみたものの、自分を制御することが出来なくなって壊れてしまった不世出の天才Syd Barrett〔シド・バレット〕がPINK FLOYD〔ピンク・フロイド〕を脱退後にリリースした1stアルバム「THE MADCAP LAUGHS」だ。
この人のバイオグラフィーは、様々な音楽雑誌でかなりの量を読んできたが、結局のところ、何故あちら側の世界に行ってしまったのか、その理由が未だによく解らない。
正直なところ、その理由を知りたいとも思わない。
筆者にとってのSyd Barrettとは、彼の曲を聴くだけで充分な存在なのである。
筆者がSyd Barrettに興味を持つ切っ掛けとなったのは、David Bowie〔デヴィッド・ボウイ〕が彼からの影響を度々口にしていたからだ。
10代の頃の筆者は「Bowieに影響を受けた」もしくは「Bowieが影響を受けた」を基準にしてレコードを買っていた時期があったので、Syd Barrettに対しては過剰な期待を寄せていた。
この「THE MADCAP LAUGHS」というアルバムは、ロックの歴史的名盤というものではないと思うし、実のところそれほど頻繁に聴く作品でもない。
PINK FLOYDのアルバムも、Syd Barrettが唯一フルで参加して彼の主導で制作された1stアルバム「THE PIPER AT THE GATES OF DAWN」より、Roger Waters〔ロジャー・ウォーターズ〕の主導で制作されたSyd Barrett脱退後の作品の方が名盤と呼ぶに相応しいと思っているし、聴いてきた回数も圧倒的に多い。
しかし、Syd Barrettというミュージシャンの魅力は、歴史的名盤云々で語れるものではないと思っている。
「THE MADCAP LAUGHS」を聴いて感じるのは、閉ざされていた心が解放されていくような、奔放なまでに自由に書かれた曲の美しさだ。
「こんな曲を書いたら、聴いた人は何を感じるのだろうか?」等という打算的なことは全く考えてないように思える。
とにかくプリミティヴなのである。
筆者もSyd Barrettのように自由でプリミティヴになってみたいと感じることもあるのだが、凡人で俗人な筆者のような人間に天才の真似など出来るはずもない。