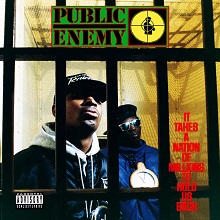【5位】Trains, Boats and Planes / The Frank and Walters

[title]
Trains, Boats and Planes
1st album
released: 1992
[artist]
The Frank and Walters (ザ・フランク・アンド・ウォルターズ)
origin: Cork, Ireland
[comment]
筆者にとって、The Frank and Walters のようなバンドは一番好きなバンドにはならないのだが、安定感が抜群で曲のクオリティが高く、いつでも安心して聴けるバンドだ。
派手さは無く流行からも程遠いのだが、彼らの奏でるしなやかなメロディーはエヴァーグリーンであり、筆者の中では Teenage Fanclub[ティーンエイジ・ファンクラブ]の近い位置にいるバンドだ。
あまりに地味すぎるので、ついつい忘れてしまいがちなのだが。
【4位】Infernal Love / Therapy?

[title]
Infernal Love
3rd album
released: 1995
[artist]
Therapy? (セラピー?)
origin: Larne, Northern Ireland
[comment]
1st Nurse ~ 2nd Troublegum では、Nirvana[ニルヴァーナ]等、米国産グランジ/オルタナティヴの強すぎる影響から脱し切れていない感じだったのだが、この 3rd は一皮むけた感がある。
演奏も歌も表現力が上がっており、楽曲の幅も広がっている。
見た目がゴツいので、ゴリゴリの音を出しそうなのだが、実はけっこう繊細な面もあり、見た目とは裏腹に器用なバンドである。
【3位】Casanova / The Divine Comedy

[title]
Casanova
4th album
released: 1996
[artist]
The Divine Comedy (ザ・ディヴァイン・コメディ)
origin: Enniskillen, Northern Ireland
[comment]
欧州人としての美学を追求したこの手の音楽は、バロック・ポップあるいはチェンバー・ポップと言うのだろうか?
当時、このアルバムと My Life Story[マイ・ライフ・ストーリー]の The Golden Mile の2枚はこのジャンルのお気に入りで、毎日のように聴いていた。
時期的にはブリットポップの末期と重なるのだが、ブリットポップとは比較にならないほど壮大な世界観を持っており、似て非なるものである(でも、Pulp[パルプ]とは、ちょっと近いかもしれない)。
【2位】Casual Sex in the Cineplex / The Sultans of Ping FC

[title]
Casual Sex in the Cineplex
1st album
released: 1993
[artist]
The Sultans of Ping FC (ザ・サルタンズ・オブ・ピン・FC)
origin: Cork, Ireland
[comment]
Sultans には "U talk 2 much" という曲があり、そのタイトルを知ったとき、「君たち、U2のこと嫌いだよね?」と訊きたくなった(笑)。
本当のタイトルは "You Talk Too Much" というのだが、祖国の英雄をこそっとおちょくるセンスが面白い。
Sultans は、「サッカー・ファンがRamones[ラモーンズ]をお手本にしてバンドを始めました」的なアホっぽいバンドなのだが、曲は意外なほど良くて、筆者にとっては U2 の何十倍、何百倍もカッコ良いと思える大好きなバンドだった。
【1位】Immigrants, Emigrants and Me / Power of Dreams

[title]
Immigrants, Emigrants and Me
1st album
released: 1990
[artist]
Power of Dreams (パワー・オブ・ドリームス)
origin: Dublin, Ireland
[comment]
The Sultans of Ping FC は祖国の英雄 U2 をこそっとおちょくってたが、Power of Dreams の場合は明確に名指しで U2 への嫌悪感を表していた。
当時の筆者は Suede[スウェード]と Manic Street Preachers[マニック・ストリート・プリーチャーズ]にぞっこんだったのだが、Power of Dreams は Suede や Manics と同じくらい好きなバンドだった。
Power of Dreams はメンバーが10代の頃この 1st をリリースしているのだが、この瑞々しい曲の数々は10代の頃にしか書けないような気がする(特に "100 Ways to Kill a Love" のキラキラ感!)。
50を過ぎたオッサンになった今でも、このアルバムを聴くと鼻の奥がツンとなり、涙が出そうになる。
~ 総括 ~
このブログでは好きなアーティストのことを書いてきたのだが、苦手なアーティストについては殆ど書いてこなかった。
しかし、筆者も人間なので苦手なアーティストはいる。
一般的に「凄い」と言われているアーティストや名盤でも、何故か筆者にはピンとこないということもけっこうある。
ブリットポップの大御所、Blur[ブラー]と Oasis[オアシス]は、最初は熱心に聴いていたのだが、何故かある日突然飽きてしまった。
それ以来、この二つの大御所は殆ど聴いていない。
90年代におけるロックの救世主、Nirvana[ニルヴァーナ]は、Bleach と In Utero は好きなのだが、何故か名盤 Nevermind は "Come as You Are" くらいしか好きな曲がない。
メタルの王者、Metallica[メタリカ]は、1st Kill 'em All、2nd Ride the Lightning、3rd Master of Puppets は大好きだ。
しかし、4th ...And Justice for All 以降、好きになれたのは 5th Metallica (通称 The Black Album) だけ。
そして、筆者がロックを聴いてきた歴史の中で最もピンとこなかった「凄い大物」が U2[ユートゥー]だ。
U2 とは出会い方が悪かったのかもしれない。
筆者は、U2 の War と同じ日に Echo & the Bunnymen[エコー&ザ・バニーメン]の Porcupine を聴いたのだが、Echo & the Bunnymen がカッコ良すぎて U2 が完全に霞んでしまったのである。
音楽の好みなんて人それぞれなので、人によっては逆になることもあるはずだが、筆者には Echo & the Bunnymen と U2 の間には雲泥の差があるように感じられたのである。
その後も U2 は All That You Can't Leave Behind までは追いかけたのだが結局嵌れなかった。
音楽もそうなのだが、U2 には音楽以外にへばり付いているもの多く、その辺が鬱陶しかったというのもある。
それを、分かり易く表しているのが、AC/DC[エーシー・ディーシー]の Brian Johnson[ブライアン・ジョンソン]が U2 について語った言葉だ。
正確には憶えていないが、「労働者だった頃の俺には金が無かったからアフリカのことを考える余裕なんてなかった。俺はコンサートに来てくれた人に募金しろなんて言いたくない。」というニュアンスの言葉だったと思う。
今回取り上げた5組のアーティストはアイルランドの英雄 U2 に嵌れなかった筆者が好きになった、90年代に活躍したアイリッシュ・ロックのアーティストだ。
U2 と比べると、吹けば飛ぶようなアーティストかもしれないが、いずれも筆者にとっては大切なアーティストなのである。